ディーゼル双発機DA42と統合電子計器G1000
2009年の12月に、ディーゼル双発機のDA42で、関東から八丈島に行ったときの
画像です。

龍ヶ崎飛行場で給油中。
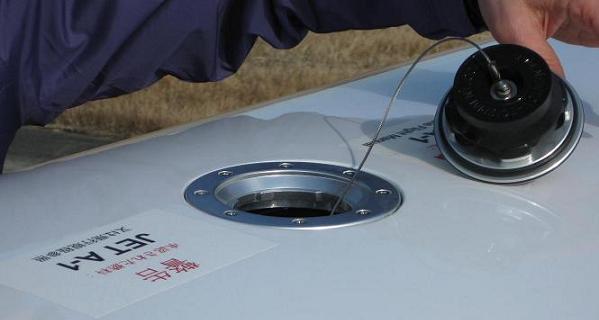
DA42はディーゼル・エンジンなので、ジェット燃料を給油します。

エンジン・ナセルの中にはサブの燃料タンクがあります。

チェックリストに従い、エンジンを始動します。
ディーゼル・エンジンなので、普通の航空機のエンジンとはだいぶ手順が
ちがいます。たとえば、「GLOW」で余熱したりします。

龍ヶ崎のエプロンを出て、誘導路をタキシング中。
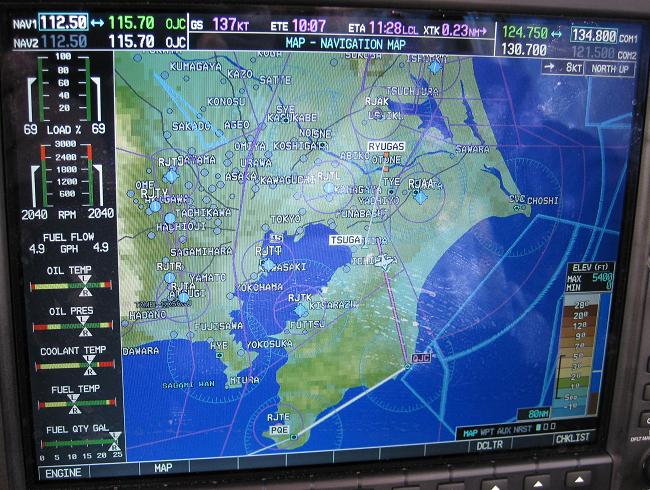
龍ヶ崎から大島までのルート。
現在、御宿VORに向けて飛行しています。

館山から三原VORに向けて飛行中のPFD。
NAVの表示窓には、受信した局のIDが文字で表示されるのが便利です。
左下の小さなマップの水色の点線の矢印はトラックベクターで、1分後の機体の
予想航跡が表示されます。これを見て偏流角を調整することができます。

大島空港にVOR/DME/LOC RWY03アプローチで進入中のMFD画面。
ミストアプローチ・コースや待機経路を含めた当該計器進入方式の全コースが
表示されています。

VORのアウトバウンド・コースから、最終進入コースに会合していくところ。
RMIやマップがあると、会合角の選定が本当にやりやすいです。

G1000の航法装置とオートパイロットを駆使して、大島のローカライザー
に会合していきます。

大島空港のエプロンで。

飛行中のG1000のインパネ。
大島からIFRで出発し、エビネ・トランジッションを飛行中です。
右下の従来型のアビオニクス装備はオートパイロットです。現在、HDG
モード、ALTモード(高度維持)で飛んでいます。

大島から八丈島までのフライトプランと、マップに表示された飛行
コース。

まもなくエビネで八丈島に向け変針します。
次のコースがRMIで表示されるのは、とても便利です。
ちなみに、次のコースは雄山VORが停波しているので、代替運用中の大路
(たいろ)VOR(TIE)を使用します。

八丈島のLOC Y RWY26アプローチのアウトバウンド・コースを飛行中。
どんどん降下しています。高度計の右のスケールが昇降計です。

ローカライザーに会合し、最終進入コースに乗りました。

八丈島空港に進入中。

八丈島のエプロンで。背景は八丈富士。

八丈島空港。

八丈島では、グラス・コックピットの夜間照明の具合を確認するために、
ローカルで夜間飛行をしました。
グラス・コックピットは、夜間飛行でも大変見やすくてきれいです。

夜間照明がきれいな八丈島空港の滑走路と進入灯。

八丈島空港にナイトで進入着陸。

八丈島からの帰りのフライトプラン。
テマー4ディパーチャーをアサインされましたが、途中で館山ダイレクトに
なったので、G1000のプランもすぐにそのように変更しました。

館山に向けて北上中のPFD画面。
この日も南の洋上は西風が強く、大きな偏流修正角が必要でした(マップ画面
に31ノットの横風であることが表示されています)。

館山を過ぎて御宿に向けて東に機首を振ると、完全に追い風になって、GSが
160ノットになりました。
羽田の進入機をさばく東京アプローチ(119.1)の管制を受けて飛んでいます。

IFR最後の都賀へのレグを飛行中のMFD画面。
こうした大きな画面に見やすいマップが表示されるのは、航法ミスを著しく
減らすことができると思います。特にIFRの雲中飛行のときは安心ですね。

オートパイロット。
現在、横方向についてはヘディング・モード、高度についてはVSモード
(昇降率一定)で飛んでいます。
「ALT ARM」というのは、高度がセットした3000フィートになると、自動的
にレベルオフする機能です。
トップに戻る